部屋が散らかる原因の一つに「とりあえず置き」という習慣があります。気がつけばテーブルの上には書類や郵便物が積み重なり、玄関には使ったままのバッグや靴が無造作に置かれる。片付けようと思っても、どこから手をつければいいかわからず、ますます散らかってしまうことも少なくありません。
しかし、ほんの少しの工夫で“とりあえず”をなくし、部屋を常にスッキリ保つことは可能です。この記事では、具体的な収納方法や習慣づくりのコツを紹介します。
1. “とりあえず置き”が起こる原因とは?
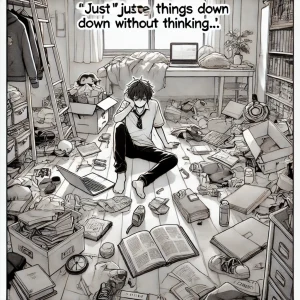
無意識の習慣が部屋を散らかす
部屋が散らかる人の多くは、特別な理由があるわけではなく、無意識に物を適当に置く習慣がついています。たとえば、帰宅後すぐにカバンをソファの上に置いたり、郵便物を玄関やダイニングテーブルにそのまま置いたりすることが習慣化すると、気づけば部屋中に物があふれてしまいます。
たとえば、カフェのテーブルを思い浮かべてください。おしゃれなカフェでは、テーブルの上に余計なものはなく、必要最低限のものだけが配置されています。しかし、自宅では「ちょっと置いておこう」という小さな積み重ねが、知らないうちに部屋全体を散らかしてしまうのです。
収納場所が曖昧だと物が迷子になる
物の定位置が決まっていないと、「ここに置いたはず」と思っていても、いざ使おうとすると見つからないという経験はないでしょうか。このように、収納場所が曖昧なままだと、出したものを元に戻さないまま、次々と新しいものを適当に置くようになり、結果的に部屋が散らかってしまいます。
たとえば、テレビのリモコンの定位置を決めていない家庭では、リモコンがソファの下やテーブルの端など、思いもよらない場所に置かれがちです。一方、決まった位置に必ず戻す習慣がある家庭では、探し物をすることがほとんどありません。
片付けのハードルが高いと後回しにしがち
収納が複雑だったり、片付けるのに手間がかかったりすると、人は面倒に感じて後回しにしがちです。特に、フタを開ける、引き出しを引くといった動作が増えると、それだけで「片付けるのが面倒」と感じることもあります。
たとえば、アクセサリーを専用のケースにしまうのが面倒で、ついドレッサーの上に置いてしまうことはありませんか? しかし、簡単に引っ掛けられる収納を用意すれば、片付けの手間が減り、習慣化しやすくなります。
では、“とりあえず置き”をなくすためには、どのような工夫が必要なのでしょうか。次に、物の定位置を決めることの重要性について解説します。
2. 物の定位置を決めるだけでスッキリ!
「ここに戻す」をルール化する
部屋をスッキリ保つために最も重要なのは、すべての物に定位置を決めることです。どこに何を置くかを決めるだけで、片付けのストレスが大幅に軽減されます。特に、毎日使うものほど、決まった場所に戻すことを習慣化すると、部屋が散らかりにくくなります。
たとえば、家の鍵を毎回違う場所に置いてしまうと、出かける前に探す時間が発生してしまいます。しかし、玄関近くのキーフックやトレーを定位置と決めることで、毎回同じ場所に戻す習慣がつき、探す手間がなくなります。
使用頻度別に収納場所を最適化
収納場所を決める際には、使用頻度を考慮することが大切です。よく使うものは手の届きやすい場所に収納し、あまり使わないものは奥のスペースを活用すると、自然と片付けやすくなります。
たとえば、毎日使うカバンをクローゼットの奥にしまってしまうと、面倒になり、その辺に置きっぱなしになりがちです。しかし、玄関やリビングのすぐ手が届く場所に専用フックを設けることで、簡単に収納できるようになります。
一目で分かる収納ラベリングの活用
収納をより使いやすくするためには、ラベリングを活用するのも効果的です。特に、家族で暮らしている場合、誰が見ても何がどこにあるかが分かるようにしておくと、片付けがスムーズになります。
たとえば、キッチンの引き出しに「カトラリー」「調味料」「ラップ・ホイル」などとラベルを貼ることで、家族全員がすぐに使いたいものを見つけられるようになります。また、子どもがいる家庭では、おもちゃ収納にイラスト付きのラベルをつけることで、小さな子どもでも片付けやすくなるでしょう。
次は、収納を考える上で最も大切な「取り出しやすさ」について詳しく解説します。
3. 収納は「取り出しやすさ」を最優先
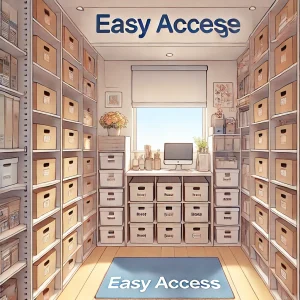
ワンアクションで取り出せる仕組み
収納のポイントは、取り出しやすさを最優先にすることです。収納スペースがあっても、取り出すのに手間がかかると、片付けるのが面倒になり、結局“とりあえず置き”が発生してしまいます。ワンアクションで物が取れる収納を意識すると、スムーズに使えて片付けやすくなります。
たとえば、調味料を引き出しの奥にしまうのではなく、コンロ横のオープンラックに置いておけば、料理中にサッと手が届きます。同様に、リビングのリモコンや筆記用具なども、フタ付きの収納ボックスに入れるよりも、オープンなトレイに置いたほうが使いやすくなります。
引き出しや扉付き収納のデメリット
引き出しや扉付きの収納は、一見スッキリして見えますが、毎回開け閉めが必要になるため、片付けが面倒になりがちです。そのため、頻繁に使うものはできるだけオープン収納を活用し、ワンアクションで取り出せるようにすることが大切です。
たとえば、よく使うカバンをクローゼットの奥にしまってしまうと、取り出すのが面倒で、ついソファの上や床に置きっぱなしにしてしまうことがあります。しかし、玄関やリビングの壁にフックを設けるだけで、カバンの収納がラクになり、スッキリした空間を維持できます。
よく使うものほどオープン収納に
片付けやすさを考えると、頻繁に使うものほどオープン収納を採用するのが理想です。収納の奥にしまい込むと、取り出すのが面倒になり、出しっぱなしの状態が続いてしまいます。
たとえば、毎日使う食器やカトラリーは、食器棚の奥ではなく、手前の取りやすい場所に収納することで、スムーズに使えます。また、リビングでは、使用頻度の高い雑誌やリモコンをオープンなバスケットに収納すると、出し入れがしやすくなります。
このように、収納の仕組みを工夫することで、片付けのハードルが下がり、部屋を常にスッキリと保つことができます。では、次に“仮置きスペース”が逆効果になる理由について考えてみましょう。
4. 「仮置きスペース」を作ると逆効果?
一時置きが習慣化すると散らかる
部屋を片付ける際に、一時的な「仮置きスペース」を作る人がいます。しかし、これは逆効果になることが多いです。一時的なはずのスペースが、いつの間にか物置になってしまい、結果的に部屋が散らかる原因になってしまうのです。
たとえば、「とりあえずここに置いておこう」と思ってカウンターや机の端に置いた郵便物や書類が、気づけば何週間もそのままになっていたことはないでしょうか? こうした仮置きスペースは、片付けを後回しにする原因になるため、極力作らないことが重要です。
すぐ片付けられるシンプル収納のすすめ
仮置きスペースを作らないためには、すぐ片付けられるシンプルな収納を取り入れることが大切です。収納が複雑すぎると、片付けが面倒になり、つい“とりあえず置き”が発生してしまいます。
たとえば、玄関にシューズラックを設置し、靴を脱いだらすぐに収納できる仕組みを作るだけで、玄関の散らかりを防げます。また、テーブルの上に郵便物がたまりがちな場合は、専用の郵便トレイを設け、すぐに整理できる環境を作るのが有効です。
使ったら戻す!を習慣化するコツ
収納を整えても、使ったものを元に戻す習慣がなければ、すぐに散らかってしまいます。「使ったらすぐに戻す」という習慣を身につけることで、部屋を常にスッキリと保つことができます。
たとえば、歯ブラシを使ったらすぐに歯ブラシ立てに戻す、ハサミを使ったら決めた引き出しに戻す、といった小さな習慣を積み重ねることで、片付ける意識が自然と身につきます。また、家族とルールを共有し、全員が同じ習慣を身につけることで、家全体の片付けが楽になります。
次は、片付けをラクにする日常の工夫について詳しく見ていきましょう。
5. 片付けをラクにする日常の工夫
1日5分のリセットタイムを導入
毎日の生活の中で、短時間の片付け習慣を取り入れるだけで部屋の散らかりを防ぐことができます。おすすめなのは、1日5分の「リセットタイム」を設けることです。例えば、寝る前や帰宅後の数分間を使い、リビングやキッチンを軽く片付けるだけで、次の日の朝を気持ちよく迎えられます。
たとえば、食事の後にテーブルを拭き、使った食器をすぐに片付けることで、翌朝の片付け作業が楽になります。こうした小さな習慣を続けることで、散らかりにくい環境を自然に維持できるようになります。
物を増やさない仕組み作り
部屋を片付けやすくするためには、そもそも不要な物を増やさないことが重要です。新しいものを購入するときは、「本当に必要かどうか」「同じようなものを持っていないか」を考えることが大切です。
たとえば、洋服を新しく買う際に、「1つ買ったら1つ手放す」というルールを作ると、クローゼットの中が物で溢れるのを防ぐことができます。また、収納スペースに収まる範囲を超えた物は手放すという基準を設けることで、自然と片付けがしやすい状態を維持できます。
定期的な断捨離で「余白」を確保
物が増えすぎると、片付けの手間が増え、収納スペースも圧迫されてしまいます。そこで、定期的な断捨離を習慣化することが重要です。1ヶ月に1回や季節の変わり目に、「使っていないものはないか?」を見直す時間を作ると、不要な物が減り、スッキリした部屋を維持しやすくなります。
たとえば、年末の大掃除や引っ越し前のタイミングで、不要な洋服や雑貨を見直すことで、物を減らしやすくなります。さらに、フリマアプリやリサイクルショップを活用することで、不要な物を手放しつつ、ちょっとした収入にもつながります。
まとめ
部屋が散らかる大きな原因は「とりあえず置き」の習慣にあります。これを防ぐためには、物の定位置を決め、取り出しやすく収納し、片付けるハードルを下げることが重要です。
また、「仮置きスペース」を作らないようにし、使ったものはすぐに戻す習慣をつけることで、部屋の散らかりを防ぐことができます。さらに、1日5分の片付け習慣を取り入れ、物を増やしすぎない工夫をすることで、自然とスッキリした空間を保つことが可能になります。
片付けは一度やれば終わりではなく、日々の小さな工夫の積み重ねが大切です。日常の中で少しずつ意識を変えることで、ストレスなく片付いた空間を維持することができるでしょう。
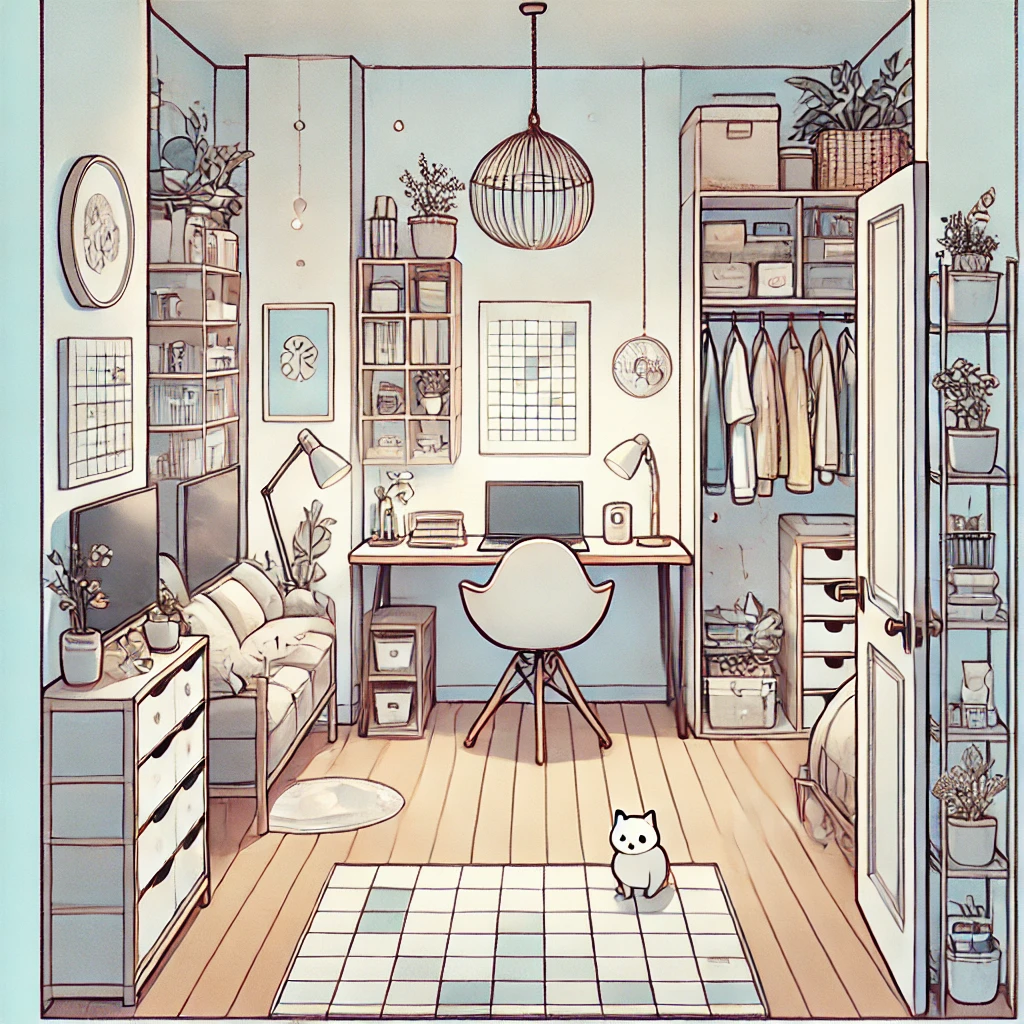


コメント